Contents
作品を守るには?最初にぶつかった悩み
作品を作って、展示して販売するにあたって、アーティストとして心配になるのはコピーされたり、模倣品を作られたりすること。
どうやって自分の作品を守るか?ということを考えた時に、知的財産権について調べた時がありました。
自らが考えた新しいコンセプトを元に制作した作品を海外の国際見本市で展示した時に、
「新しいアイデアなので、知的財産で守れるか検討した方が良い」
と何人かにアドバイスをいただいたのがきっかけでした。

国際的な展示会に出展するということは、それだけ作品が多くの目に触れ、模倣のリスクも高まるということでもあります。
だからこそ、自分の作品をどう守るかを考えることは、海外発信をするアーティストにとってとても大切だと感じました。
知的財産権の基本:5つの権利を検討してみた
アートやファッションの分野は、模倣品が世の中に溢れている世界。
特殊な新しい技術が制作に関わっていたらそれを保護することはできても、デザイン、アイデア、コンセプトに関しては恐らく守るのは難しいのではないかと思いながら調べました。
結論としては、予想していた通りでした。
デザインに関しては、よほどの資金力のある大手ブランドであれば保護することも可能ですが、個人や小規模ブランドにとっては現実的に難しい、というのが実感です。
以下、私が考察した概要をまとめました。自分で調べた内容に加えて、5人以上の弁理士さんに実際に伺ったお話を元にしています。
知的財産権について、よく知らないけれど気になっている方に向けて、調べた内容を共有することで何かのヒントになればと思います。
なお、私は知的財産権の専門家ではなく、弁理士の資格も持っておりませんので、ここでの内容はあくまでも一個人の調査と考察によるものである点をご了承ください。
疑問点がある方は、ぜひ弁理士さんに直接ご相談ください。
さて、知的財産権にもいろいろな種類がありますが、アートに関係がありそうな以下の4つの権利について検討しました。
私は普段、ハンドペイントの作品を制作しているのですが、それを例にしながら検討結果をご紹介します。

1. 著作権(Copyright)
保護範囲: 文芸、学術、音楽、美術、演劇、映画などの著作物。手描きの絵柄や装飾など創作性のある表現も対象範囲。
限界: 形や構造、機能的な部分は保護されない。また、他人が似たような作品を作っても、絵柄が違えば著作権侵害にはならない可能性が高い。
結論 : 作品そのものを保護することはできるが、模倣品から権利を保護することは限界がある。
2. 意匠権(Design Patent / Industrial Design)
もし可能性があるなら意匠権くらいかな?と思っていました。
保護範囲: 物品の形状・模様・色彩などの外観デザイン。新規性と創作非容易性の要件がある。つまり、誰でも思いつくようなデザインや、既存のデザインを組み合わせただけのデザインは、取得が難しい。
課題: 類似の幅が狭く、形や大きさ、全てについて登録で網羅するのが難しい。
多様なデザインやサイズがある場合は、一つひとつ登録が必要で、コストや手間が大きい。
つまり、独自のデザインを考えた時にそれを申請することは可能ではあるが、形や大きさも含め申請されたものに限られる。それを逸脱した模倣品が出た場合には意匠権侵害にはならない。
(例として、自分は正方形のデザインだったが、長方形のデザインで模倣された場合は保護されない、など)
服飾、ファッションの世界でもデザインを守るのは難しい、と服飾学園のサポートをされている弁理士さんからも聞きました。
現実的な運用:
大手ブランドはコストをかけてでも登録しているが、個人や小規模事業者には現実的でないことが多い。(例として、某有名ブランドのバッグや靴などは全てのサイズで意匠権登録されている。それには大きなコストがかかる。)
結論 : 個人や小規模事業者としては、少数の固定したデザインであれば意匠権で保護することは可能。一点物などでいろいろな作品を制作している、また絵画などの場合は現実的に保護は難しい。
3. 特許権(Patent)
保護範囲: 技術的発明(構造や方法に新規性・進歩性があること)。進歩性とは、容易に考え出すことができないことです。
対象外: 既存の技術の組み合わせは特許としての「発明」にはならない。
結論 : 作品の制作工程に新しさと簡単には思いつかない技術が含まれていない限り該当しない。
4. 実用新案権
保護範囲: 製品の形状・構造・組み合わせに関する「考案」。一般的に、特許権より新規性・進歩性が低く、簡易な技術的工夫などで申請されるケースが多い。
課題:「技術的に新しい工夫」が求められるが、特許より条件が緩い。
審査なしで登録されるため、権利の有効性に関する不確実性が高い。
特許権に比べて権利の効力が弱く、抑止力が弱い。
実体的な審査を経ずに登録されるため、その後無効になるリスクもある。
権利行使後に無効になった場合、権利者が損害賠償責任を負う可能性もあることに注意。
結論 : 著作権より緩いとは言え、作品の制作工程に新しさと簡単には思いつかない技術が含まれていない限り該当しない。
その他の豆知識
🔁 国による登録ルールの違い
知的財産権は、国によっては「その国で思いついたものはまずその国で登録しなければならない」というルールがあります。アメリカなどがその代表で、これに反すると罰金などが科される場合もあるため、海外在住の方は申請の順番にも注意が必要です。
⚖️ ヨーロッパにおける審査の緩さとリスク
ヨーロッパでは、知的財産権の登録自体は比較的容易ですが、実際に権利行使をしても訴訟で負けてしまうリスクもあるため、登録だけで安心はできません。
考察のまとめ
冒頭にも書きました通り、
結論として、私の作品は現行の知的財産権で完全に守ることは難しい、ということがわかりました。
それでも、アーティストとして私にできることは、模倣されても自分の作品が選ばれるような、ブランド力のある作品を作り続けることだと感じました。
そして、少なくとも「これは私の作品です」と証明できる仕組みは必要です。
その意味で、商標権の登録は現実的かつ有効な一歩だと思います。

商標権については、私自身のにがい経験も含めて、あらためて別の記事で詳しく書く予定です。
リアルな内容になると思いますので、そちらも読んでいただけたら嬉しいです。
海外展示会への出展ガイドやその他の海外修行や教室運営のお話などは過去の記事をご覧ください。
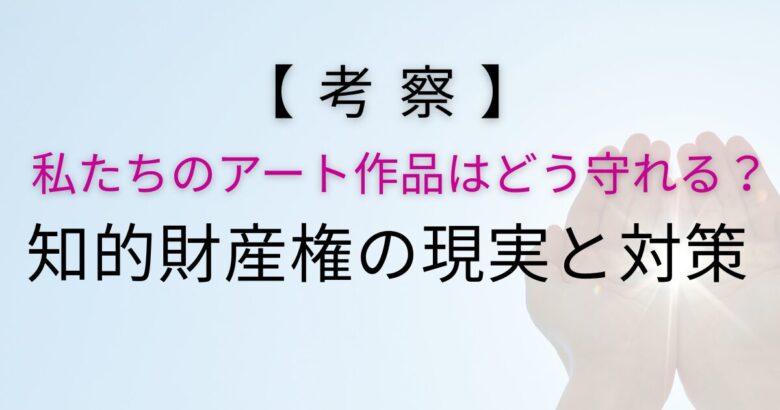

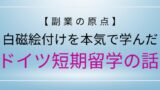
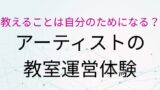
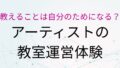
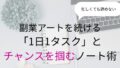
コメント